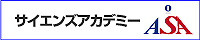2008.12.15 Mon
観点というものについて、自分を観て検べる場合に限って考えてきたが、自分以外の対象(人や物や社会や事件など)を観る場合にも、観点を持たないで見たり聞いたり、また思ったり考えたりするということはほとんどないのではないか。
観点という言葉を広辞苑で調べてみると「観察・考察するときの立場や目の付けどころ。見方。見地。『観点が違う』『観点をかえる』」とあった。人や物や社会を観たり考えたりする場合には、意識するしないに関わらず、何らかの立場に立っており、またその立場の違いによって目の付けどころも違ってくる。観え方聞こえ方捉え方が違ってくる。
人が何かについて、それは何だろう、どういうことだろうと捉えようとするとき、そこには観点が要る。ある観点に立ってこそ、そのことについての思い考えが頭に浮かぶのだろう。研鑽は無固定前進の考え方と言う。その意味は研鑽の中では、この観点というものが固定されないということのように思う。今まで、研鑽というものについて、頭に浮かぶ表面の思い考え主張にとらわれないという程度の認識であったように思うが、その内実は観点が固定しないということとも言えるのではないか。観点が固定しないから、いろいろな観点から、いろいろな角度から物事を捉えられる。いろいろな角度から物事が浮き彫りになってくるから、いろいろな可能性も観えてくる。
ここで研鑽の実現、言ってみれば観点を固定しないということは如何に実現されるかというテーマが出てくる。物事に対処するときなどには、自分の感覚であることの自覚の上に、さらに、その事を自分はどういう観点に立って、どう捉えているかということの把握(認識・自覚)が要るのではないか。
ここまで来ると、ひとりではなかなか成され難いのではないか。多くの人(観点)の集まる研鑽会においてこそ、自分の観点の自覚や、いろいろな観点の可能性も生まれやすいのだろう。現実の組織の運営・経営において研鑽会が欠かせないというのも、案外この辺の理由からかもしれない。
2008.12.14 Sun
観点という言葉を使ってきたが、自分を観るときの目の付けどころ、自分を観て検べるための手がかりという程度の意味あいで、テーマとか自分への問いかけと言ってもよさそうだが、言葉をいろいろ使うと思考の混乱をきたす面もあるかと思い、観点、観点と言ってきた。
自分を観て検べるとき、どのような観点をとるかによって、自分について浮き彫りにされるところが違ってくる。そういえば自分が「人生を知るための研鑽会」や「自分を知るための研鑽会」に参加したときのことを思い出す。どちらの研鑽会においても、スタッフの人の出してくれた問い(観点・テーマ)を、自分への問いかけにして自分の中を観て検べる、そんなことをしたなという印象が残っている。どちらも内観体験のあとの参加だったので、研鑽会の場で自分が内観しているみたいな感覚もあった。
振り返ってみると、どちらのコースにおいても、人生を知るために、また自分を知るために、幾つかの観点(自分への問い)が用意されていたように思う。一週間の過程というのは、そういう観点でプログラムされていたという印象が残っている。
各コースの性格の違いというのは、観点のとり方の違いとは言えないだろうか。自分を知るためのコースでは自分が知れていくように、自分というものが浮き彫りにされていくようにと、幾つかの観点がプログラムされている。人生を知るためのコースでは、自分の人生が知れていくように、自分の人生というものが浮き彫りにされていくように、幾つかの観点がプログラムされている、そんなふうにも言えるのではないか。
自分を知るための内観コースにおいても、自分を知るために、三つの観点や、<嘘と盗み>とか<養育費(の計算)>という観点が用意されている。そして最近は、参加者が望むなら、その人が自分で焦点を当てて検べてみたいというあたりを観点にして、内観するということも行われるようになってきた。例えば<劣等感>とか<人の話に対する自分の聞き方>とか。このあたりが内観コースの特質の一つになってきていると言えないだろうか。自分に対して独自の観点を用意して自分を観て検べるということだ。こういうことは他のコースではやりにくいのではないか。
2008.12.14 Sun
観点ということで思いつくまま書いてきて、改めて内観法に用意されている三つの観点(①世話になったこと②して返したこと③迷惑かけたこと)も、自分を観て検べるための手がかりだと言うことはできるにしても、三つの観点に含まれる内容というか、三つの観点で自分を観て検べることで内観者に齎される気付きや洞察には、何か計り知れないものがあるように思う。
身近な人に対しての自分を年代を区切って、①の観点で検べ、次に②の観点で検べ、さらに③の観点で検べるというように順に観点を変えて観るわけだが、この三つの観点ごとの個別の気付きが内観者の中で起こるのではなく、この三つの観点(で検べること)が組み合わさって、身近な人に対する自分というものが浮かび上がってくる。深い浅いはあるにしても、自分という存在の生い立ちや成り立ちに対する何かしらの気付きや洞察がなされる。
小学生にも分かりやすい観点(テーマ)だ。この三つの観点は、ごくありふれた常識的な言葉で表現されているが、この三つの観点で自分を観て検べることにより内観者に齎されるものは、とても大きなもののような気がする。三つの観点は、内観法の創始者吉本伊信氏ならではの想像力・創造力の産物というほかない。
しかし、内観法の狙うところは、何がしかの気付きや洞察というものでもないように思う。吉本伊信氏の言を借りれば「どんな境遇にあっても、幸福に生きることが出来る心境になること」だ。内観法の三つの観点は、人の心境(心の状態)や境地を主眼として考案されたものだということは、忘れてはならない。
内観コースの中で用いられる観点も、自分を観て検べるための手がかりであると言えるにしても、ある意味それも表面のことで、あくまでその人の心境(心の状態)が主眼であるならば、その人の幸福な心境への手がかりとして設定されなければならない。
2008.12.13 Sat
内観の中での観点というのは、自分を観て検べるための手がかりだと捉えると、その人が自分のことを検べられるなら、どんな観点(言葉)を持ってきてもよいと言えるのではないか。言ってみれば、その観点を手がかりにして、自分のことを観て検べられたら、その観点はその人にとって適切だったと言えるのではないか。
内観コースの中で、「人の話に対して、自分はどういう聞き方をしているのか」という観点で自分を検べてみた人が今までに何人かいる。でもこの観点はいささか高度(?)のような気がする。本題に直接入っていくという感じで、最初からこういう観点で自分に問うことができたらいいが、こういう観点ではピンと来ないという人もいると思う。
今回の内観コースでは「人の話を聞けない自分(を探す)」という観点で自分を検べた人がいる。内観コースに参加する前に奥さんに「あんたは人の話を全然聞けない」との指摘を受けたようで、その辺を検べてみたいということであった。最初は「聞けない自分」の実例をなかなか見つけられないようであったが、繰り返し検べるうちに実例が次々と出てきた。奥さんの指摘を受けたときには「そう言われてみればそうかな」ぐらいの思い方だったのが、いくつもの「聞けない自分」の実例を前にして、「聞けない自分」のことが身に沁みて感じられてくる。そこから自ずと「自分はどういう聞き方をしているのか、自分の中はどうなっているのか」という問い(観点)がその人の中に出てくる。自分の実状を思い知ることで自分を検べる意欲も出てくる。そこから本題に入っていく。
ある意味では「聞けない自分」という観点で自分を観るのはしんどいことかもしれない。でも「聞けない自分」を探すことでいくつもの実例が出始めると探す面白みも出てくるように思う。そして、自分の中から「自分はどういう聞き方をしているのか、自分の中はどうなっているのか」という問い(観点)が出て来る頃には、そろそろ検べる面白みというのも感じ始めて来るようだ。自分を検べる面白みがなければ、何を好き好んで・・・
・「自分の聞き方」というより「聞けない自分」という観点での方が、自分を捉えやすいように思う。「聞けない自分」の中には、反応として何かしらの気持や感情の起伏が起こることが多い。そういう反応は(どういう内容のものかということは別にしても)意識されやすいから、それが「聞けない自分」を探す手がかりになるような気もする。
2008.12.12 Fri
・観点という言葉を広辞苑で調べてみると「観察・考察するときの立場や目の付けどころ、見方。見地。『観点が違う』『観点を変える』」と書いてあった。「・・の立場や目の付けどころ」とあるが、内観するとか自分を検べるという場合、立場というより目の付けどころという方が、自分には分かりやすくピッタリくる。
自分のどこに目を付けるのか、自分のどこを観るのか、自分のどこに焦点をあてるのか。検べることで自分の何が、自分のどのあたりが浮き彫りになってくるのか。観点(目の付けどころ)が違えば、浮き彫りになってくるところも違う。観点を変えて、自分をいろいろな角度から検べる。自分のいろいろな面が浮き彫りになってくる。
・ある観点(テーマ・言葉)で自分を観て検べるという場合、その観点というのは一つの手がかりと言ったらいいだろうか。自分を検べるために仮に用意するものといったら言い過ぎか?
観点というのは言葉で表現される。例えば劣等感というのもなんらかの心的状態を指しての言葉だ。その観点(言葉)を手がかりに自分を観て検べる場合、その人はその言葉とその言葉にまつわる意味あいを頭に置いておくのだが、あくまで自分のありのままを観て検べようする。そういう中で自分の何らかの心的状態が浮かび上がっくることがある。それを劣等感と言ってもいいわけだが、そこを直視(客観視・自分から離して観ること)できたら、今あるその劣等感という何らかの心的状態は変化して消えていく。その人の中から劣等感という心的状態がなくなれば、劣等感という言葉も要らないわけだ。そうすると劣等感という観点(言葉)は自分を検べるために仮に用意した手がかりという程度のものと言える。
実際にはそう簡単にはいかないようで、自分を観て検べる場合には、内容的にも時間的にもそれなりの過程は要るが、原理的にはこういうことかと思う。
振り返ってみれば、劣等感という心的状態も、決して実体的なものでなく、何かのきっかけで現れた一時的(?)状態であったことに気付く。
言葉にすると何か固定されて、言葉で表現されるものが何か実体としてあるかのごとくにイメージしやすいが、そのことが自分を観たり検べたりし難くさせるのではないか。下手すると「劣等感とは何か」と考える方に気が行ってしまって、自分を観るとか自分を検べるとかにならない。
観点(手がかり・テーマ)というのものを適切に設定する必要があるわけだが、その受け取り方に何か固定したものが入りやすいのではないか。