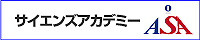内観にみる人間観8(人間観というもの)
乳幼児は親に依存して(頼って)生きる。生きていくためには親にほとんどすべてのことを世話してもらわなければならない。また、はいはいして動き回ることが出来るようになると、親の方に寄っていく。抱かれると喜ぶ。満足げな様子である。抱かれると嫌がるときもあるだろうが、やっぱ親が近くにいると安心しているようだ。親がいなくなると不安になって泣く。
子にとって親は、共にいると安心できる存在、いろいろ世話されることで満足を与えてくれる存在と言ってもいいかもしれない。子が自ら親の方に近寄って行ったり、親がいなくなると泣いたりするところを見ると、その子は、親が自分にとってどういう存在であるかを知っていると言えるのではないか。言ってみれば、その子は、親を安心できる存在、満足を与えてくれる存在と観ているということだ。
ちょっと奇異に聞こえるかもしれないが、その子が、そういう親(人間)観を持っているとは言えないだろうか。意識はされてはいないだろうが、その子のベースにそういう人間観(親観)がある、ないしはその時にはそういう人間観が形成されつつあるとも言えるのではないか。その後の成長過程でいろいろ変化はするだろうが。
大人になっても誰の中にも人間観というものがあるのだと思う。自分にとって人(自分と他人)というのはどういう存在なのか、自分は人をどう観ているのか、そういう人間観が、自分に意識されているかどうかにかかわらず、自分の中にはあるようだ。
人間というものをどう捉えるか、どう観るかという人間観はいろいろな観点で言えることだと思うが、存在という観点から観て、人を個別に存在すると観るのか、一つに繋がって(溶け合って)存在すると観るのか、これも人間観の違いと言えるだろう。
内観法は、内観者が、存在という観点から自分(人)を観ていく、そして内観者の中に、存在という観点からの人間観が形成されていく、そのように仕組まれているような気もする。
人に対する自分を観るということは、人との関わり方を観るということだ。人との関わり方とは、自分の存在の仕方といってもいい。すべてを受けて存在している、決して個別には存在できない。そういう存在の仕方。自分の存在の仕方を知ることで、人の存在の仕方を知る。人と人が一つに繋がった存在の仕方を知る。そこに新たに形成されてくる人間観がある。
子にとって親は、共にいると安心できる存在、いろいろ世話されることで満足を与えてくれる存在と言ってもいいかもしれない。子が自ら親の方に近寄って行ったり、親がいなくなると泣いたりするところを見ると、その子は、親が自分にとってどういう存在であるかを知っていると言えるのではないか。言ってみれば、その子は、親を安心できる存在、満足を与えてくれる存在と観ているということだ。
ちょっと奇異に聞こえるかもしれないが、その子が、そういう親(人間)観を持っているとは言えないだろうか。意識はされてはいないだろうが、その子のベースにそういう人間観(親観)がある、ないしはその時にはそういう人間観が形成されつつあるとも言えるのではないか。その後の成長過程でいろいろ変化はするだろうが。
大人になっても誰の中にも人間観というものがあるのだと思う。自分にとって人(自分と他人)というのはどういう存在なのか、自分は人をどう観ているのか、そういう人間観が、自分に意識されているかどうかにかかわらず、自分の中にはあるようだ。
人間というものをどう捉えるか、どう観るかという人間観はいろいろな観点で言えることだと思うが、存在という観点から観て、人を個別に存在すると観るのか、一つに繋がって(溶け合って)存在すると観るのか、これも人間観の違いと言えるだろう。
内観法は、内観者が、存在という観点から自分(人)を観ていく、そして内観者の中に、存在という観点からの人間観が形成されていく、そのように仕組まれているような気もする。
人に対する自分を観るということは、人との関わり方を観るということだ。人との関わり方とは、自分の存在の仕方といってもいい。すべてを受けて存在している、決して個別には存在できない。そういう存在の仕方。自分の存在の仕方を知ることで、人の存在の仕方を知る。人と人が一つに繋がった存在の仕方を知る。そこに新たに形成されてくる人間観がある。
内観にみる人間観 | - | trackbacks (0)